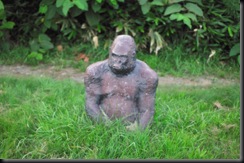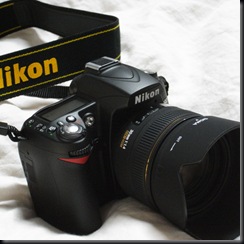セキュリティの強化だかなんだかしらないが、MSのネットワークは本当にめちゃくちゃだ。 めちゃくちゃというか、勝手にどんどん仕様が変わっていく上に、既存OSとの互換性も無く、そのサポートも無い。Windows7のヘルプなんて、みんな英語でさっぱりわからん!
と、みかこさんのVAIOが我が家のLANに参加したときに、かなり頭にきながら共有設定した事は記憶に新しいが、このたび私のPCのOSをWindows7にアップデートして、またもや同じ思いをするとは…
そもそも、インストール時に聞かれる、あれは、何だ?
ホームネットワーク、社内ネットワーク、パブリックネットワークだぁ?ネットワークにそんな分類があるかってぇの! 普通に考えると、自宅のネットワークだから、ホームネットワークを選ぶのが正解じゃないかな?って思うけど、説明には、「すべてのコンピュータが自宅にあり、全機が認識されている場合」なんて書いてあるわけ。 言葉通り考えたら、インターネットに出られなくなってしまうじゃないか….ってんで、もしかしてパブリックかなぁ、なんて思ったりもする。おまけに、迷ったらパブリック選べばぁ?なんて書いてあるから、パブリック選んじゃう人多いと思う。 ノートPCだったら特に、主に自宅で使う人でも、パブリック選びそうだよね。
でもって、このホームだなんだって言葉が、VISTAと微妙に違うわけ。確かVISTAは、プライベートとパブリックだったかな…設定ダイアログの表示も違うし、いい加減にしてって感じだなぁ。
というのが第一の難関。いろいろ悩んだあげく、VISTAの方はプライベート、Windows7の方はホームネットワークにする。
実は、Windows7の場合は、もう一つ落とし穴があって、「ホームグループ」ってやつ。 これ、ホームネットワークと全然関係ないから! 説明を読むと、これにすると、ファイル共有も、プリンター共有も実にスムーズに、簡単に設定できるような事が書いてあるけど、これって、Windows7同士だけの話で、VISTAもXPも使えないから、まったく意味の無い話。家中のWindowsを7にしろってかぁ?
しかし、ようやっとここまでたどり着いても、相互に見つかったり、見つからなかったり、アクセスできたりできなかったり。なんじゃこりゃ。 さっきまでアクセスできていたのに、いったん設定を変えて戻したら、もうアクセスできない。 不安定なんだよねぇ。 1時間ほったらかしたら、接続できるぞぉ~なんてお話もあるけど、ネットワークってそんなにいい加減なのかぁ?
で、思うに、これは、どうやら、コンピュータ名をちゃんと見つけられないんじゃないかなと思う。 PC同士ってのは、LANの中では、MACアドレス(Appleのじゃないよ)というアドレスでお互いを認識しあっているわけだけど、そのMACアドレスはレイヤー2と呼ばれる下層で使われるもので、我々が良く目にするのはその上の、レイヤー3で使われるIPアドレス。LANなら、ローカルIPアドレスと呼ばれるものだ。このIPアドレスとMACアドレスは、特殊なものではないので、Windowsのネットワークでも特に問題は起きないのだが、その上が問題。
インターネットでは、host.hajimesan.net みたいなホスト名・ドメイン名で通信先を示して、それを、DNSという仕組みでIPアドレスに変換しているのだが、WIndowsは、LANの中ではコンピューター名とIPアドレスを結びつけて、相手を示している。この名前解決を行うのが、WINSってやつだ。こいつが、どうもまともに動かないわけ。誰がWINSサーバーになるかがころころ変わるし、情報はキャッシュされるから、古い情報が残っていたりすると、おかどちがいのIPアドレスが返ってきて、全然つながらないんだよね。 これに、DHCP と呼ばれる、IPアドレスを自動的に割り当てる仕組みが加わると、更に混乱してしまうわけだ。
というわけで、まずは、ルーターのDHCPの割り当てアドレスを制限しましょう。たとえば、192.168.1.20 ~ 192.168.1.30 くらいまでに制限しちゃう。こうしておけば、192.168.1.1 はルータだとして、.2 ~ .19 までは、自由に使える事になる。で、LAN内のPCは、DHCPは止めて、全部IPアドレスを振る。 もしそれが面倒なら、ルーター側で、このMACアドレスのIPアドレスは、DHCPでこのアドレスを固定的に振ると設定しておけば、PC側はDHCPの設定のままでもOK。
でもって、お次は、DNSに対して、hosts ファイルを書くように、WINSなんて使わねぇって気持ちで、LMHOSTSファイルを書く。なんて書くか?そりゃ固定的に振ったIPアドレスと、LANの中のコンピュータ名をペアで書くのだ。書き方はGoogle様に聞けばすぐにわかる。おっと、楽天ツールバーで検索した方が、楽天ポイントが溜まって良いかも。
ここまでやれば、いつでも安定して、LAN内のPCがお互いに認識できて、かつ、プライベートだとかホームに設定しているので、お互いに信頼している前提でWindowsが処理してくれるので、ファイル共有もプリンター共有も問題無くできるようになる。
が、たぶん、落とし穴があるかも。うちでは全PCに私とみかこさんのアカウントを設定して、ちゃんとパスワードも設定しているから問題無いけど、アカウントを設定していなかったり、面倒だからってパスワードが設定されていなかったりすると、たぶん、もっと苦しむ事になる。 Windows7のデフォルトでは、確か、ID/パスワード管理ではなくて、Windowsが管理する みたいなのがデフォルトだったので、そのままではダメかもしれない。私は、Windowsに管理してもらいたいとは夢にも思わないので、速攻変更してしまったので、わからないし、もう共有できちゃったから、今から確認したいとも思わない。
パスワードは、今時、パスワード無しのアカウントなんて作るの止めようね! そういうの、オジサンって呼ばれちゃうよぉ~。
あ、それから、なんちゃらHOMEエディションとかの、中途半端なエディションのOSの場合も、もっと苦しむかもしれない。 使ったことないからわからないけど、ネットワークでつながってナンボのこの時代に、こういう制限するかいな?という酷い制限がされているらしい。全部のPCに同じIDとパスワードを設定すれば大丈夫なのかな?
最後に、NASとかのSAMBAね。 (SMBではなくてUSCの設定でした。)これはVISTAの時は、レジストリ変更とかしなければならなかった記憶があるけど、Windows7は、アカウントのところの設定で、スライドバーで一番甘い設定にすれば大丈夫だった。 VISTAで相当たたかれたんだろうね。
SAMBAに関しては、うまくいかない場合は、河野さんのブログに丁寧な説明がありました。
以上。 WIndows7 にして、WIndowsファイル共有、プリンター共有に苦労して憂さ晴らしに書いてみました。 あーだこーだやっているうちに、なんとなくつながったぜ!みたいなところもある(プロにあるまじき話しだなぁ)し、きっと、嘘八百な部分があると思うけど、つながらないで夜も眠れない人は、試してみたら?
1つ大事かもしれない事を書き漏らしたので、追記。
システムのプロパティの、コンピュータ名タブに、「変更…」ボタンってのがあって、これを押すと、「所属するグループ」というのがあるんだけど、我が家の場合は、これを「ワークグループ」にして、全PCで同じワークグループ名を設定している。
同じにしておくと、きっと良いことがあるに違いない。