index
キャンプグッズ使ってますか?
買って持っているだけの物、多くありませんか?
夫婦関係に、味噌汁は必要ですか?
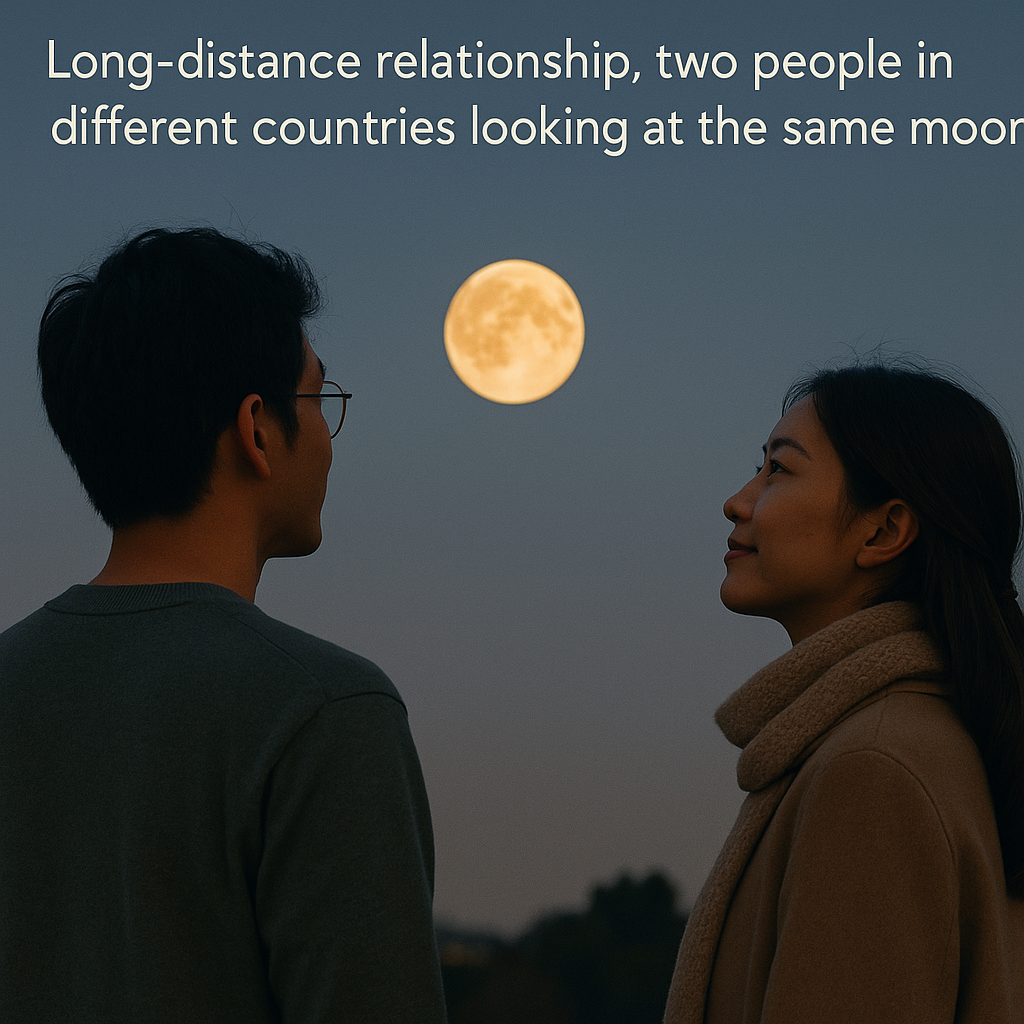
1. 手に取れるものだけを信じてきた時代
トイレットペーパーやマスクの買い占め、今は、金(ゴールド)の行列。
日本人は、手元にないと落ち着かない民族かもしれない。
「持っている」ことでしか安心できないのは、
私たちの“農耕民族の記憶”がまだ生きている証拠だ。
所有することが安全の象徴だった時代。
預金通帳の数字、家、肩書き、車、あらゆるものが「自分を守る壁」だった。
けれど、いま私たちは少しずつ、その壁の中で息苦しさを感じ始めている。
2. 信頼のかたち ― 欧米と日本のちがい
欧米では「信用」や「契約」が社会の土台にある。
それは、見えない約束を信じる文化。
一方で日本は、目に見える関係性や、
共有された“場の空気”の中に信頼を築いてきた。
だから日本人にとって信頼とは、
遠くの相手を信じることよりも、
隣にいる誰かと調和することだった。
その違いが、国際社会の中では「未成熟」と映るのかもしれない。
けれど実際は、成熟の“方向”が違うだけなのだ。
自分を信じる力の欠如
もう一つの違いは、「信じる対象」がどこにあるかだ。
欧米では、信頼の中心が“自分自身”にある。
失敗しても「またやり直せる」と信じる力が、
所有から自由でいられる土台になっている。
一方で日本では、
「自分」という存在を社会の中の立場や肩書きで定義しがちだ。
どこの大学を出たか、どんな会社にいるか、
その“位置”こそが自己の証明になっている。
だから、地位やモノを失うことは、
自分の存在そのものを失うように感じてしまう。
これは能力がないからではなく、
“自分を信じる訓練”をしてこなかった文化の結果だと思う。
もし自分の力を信じられるなら、
裸一貫でももう一度立ち上がれるという確信が持てる。
そうなれば、モノに縛られず、
“持たない自由”の中にこそ安心を見いだせるはずだ。
3. 遠距離恋愛とゴールド投資
遠距離恋愛を苦手とするのも、
ETFより地金を求めるのも、根は同じ。
日本人は「形」「距離」「所有」を通して安心を感じる。
それは不器用なようでいて、
確かさに重きを置く誠実な感性でもある。
同じ月を見上げながら、
遠く離れていてもつながっている二人のように、
見えない関係を信じる力が、
これからの時代にこそ求められている。
4. 所有から信頼へ ― 次の成熟へ
もしこれからも国際社会と共に歩むなら、
「持つ安心」から「信じる安心」へ、
少しずつ重心を移していく必要があるのかもしれない。
ゴールドも愛も友情も、
本当は“距離を超えて続くもの”。
見えないものを信じる力——
それは、所有から解放される勇気であり、
日本人が次の成熟へ向かうための静かな一歩なのだと思う。






