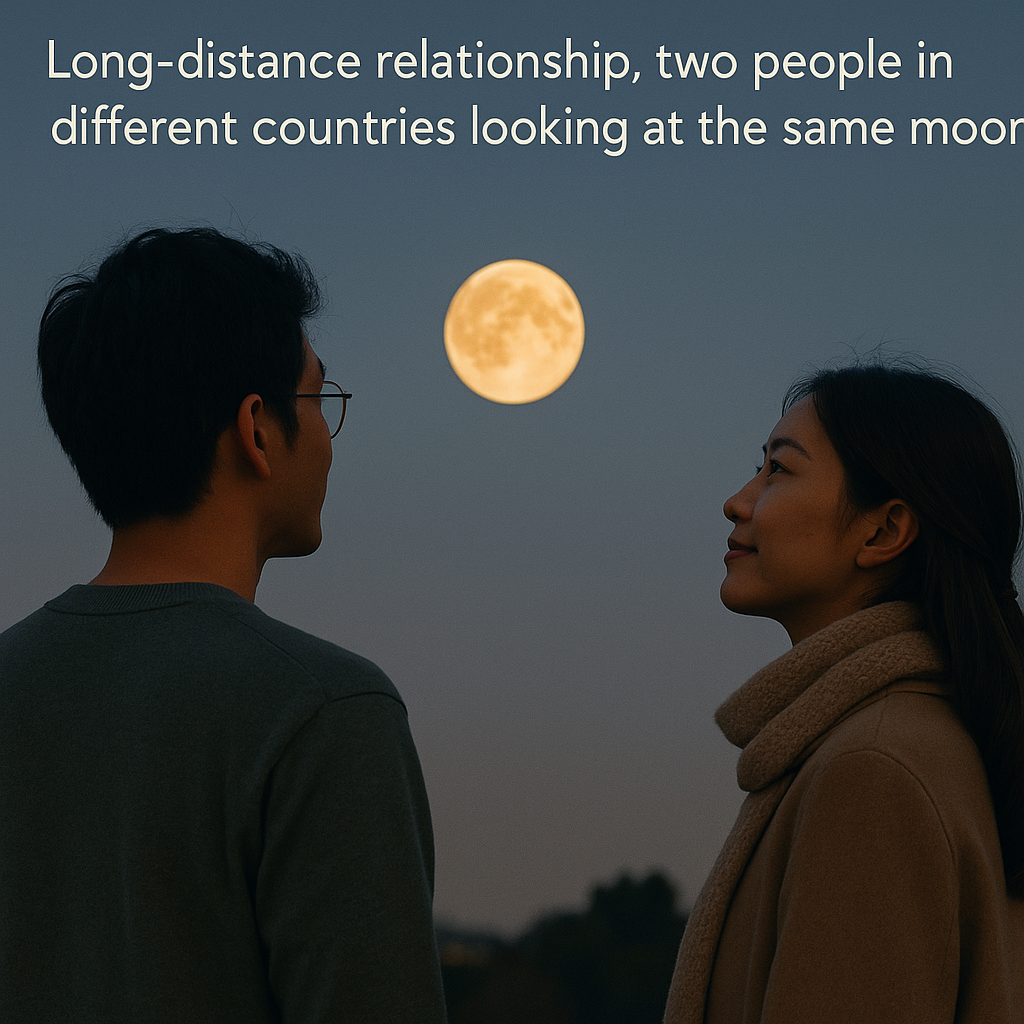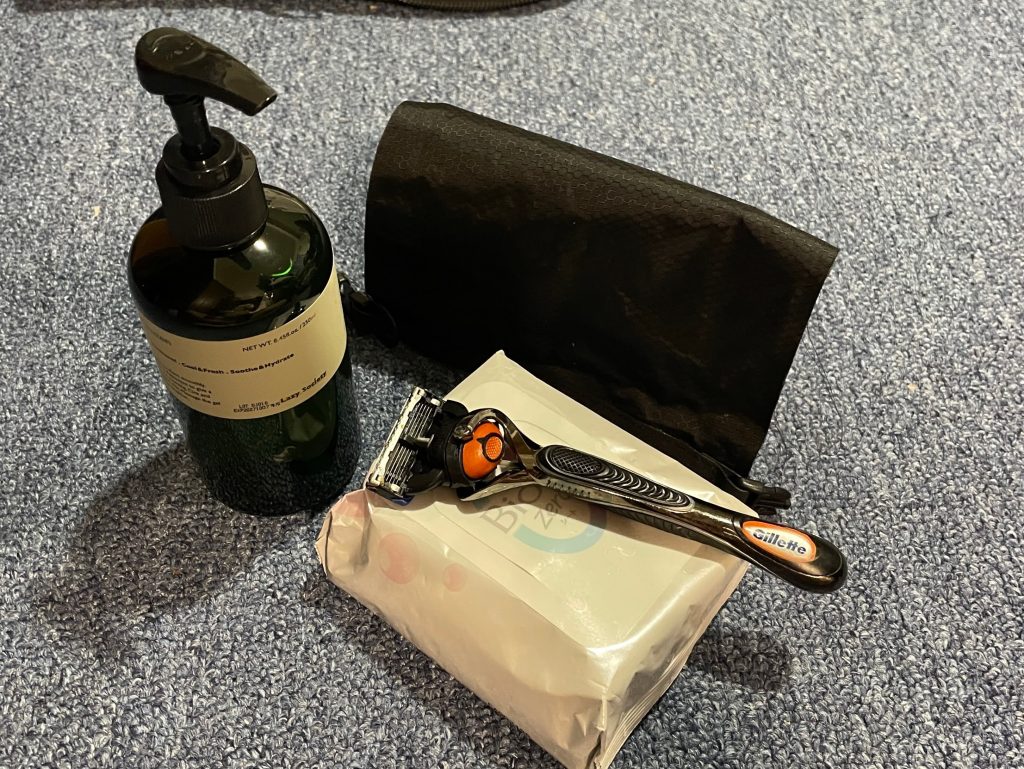
■ はじめに:ひげ剃りに“派閥”なんていらない
ひげの剃り方は、本当に人それぞれだと思います。
深剃りの感触が好きな人もいれば、
朝の準備を少しでも効率良くしたい人もいる。
どちらが優れている、正しいという話ではなく、
ただ自分の生活の流れに合う方法を自然に選んでいるだけ。
私はそう感じています。
今回まとめた方法も、
ふだんの習慣を否定したり置き換えるものではありません。
むしろ、
「必要なときに静かに取り出せる“もうひとつの手段”」
そんな軽い位置づけです。
たとえば——
- 家族が寝ている早朝
- ホテルで同室者に気を遣う夜
- 静かな場所で音を立てたくないとき
- 外出直前に“ちょっと整えたい”瞬間
こうした「たまに困る場面」は、
普段どんな道具を使っている人にも起こり得ます。
私自身も、ひげ剃りの派閥意識があるわけではなく、
生活に合わせて自然に使っているだけ。
そのうえで今回の方法を試してみたところ、
ひげ剃りの自由度がひとつ増えたと感じました。
この記事はその体験の記録です。
■ きっかけ:風呂場に行くのが面倒な日がある
普段は風呂場でT字カミソリを使っています。
ただ実際には、
- 朝バタバタしている
- すぐ出かけたい
- 夜に風呂へ入れなかった
- 仕事中に“ヒゲが伸びたな”と気になる
こういうとき、
いちいち風呂場へ行くのが面倒に感じる日があります。
電気シェーバーの便利さも理解しているけれど、
私の場合はT字の剃り味が好きで、
できればそちらを使いたい。
そこで、
「風呂場に行かなくてもT字で剃れる構成」
を考えてみることにしました。
■ 今回使ったのは、この4つ
今回の“風呂の外でT字を使うシステム”を組んだのは、この4点です。
このうち、IKKEIケースだけは後で説明しますが、
「カミソリ本体を清潔にしまうため」の役割です。
これがあるだけで外でも安心して使えます。
では、それぞれのアイテムの役割と理由を紹介します。
■ 1. ジレット プログライド
——安全で扱いやすく、深剃りもできる中心の存在

今回の方法が成立した理由の半分は、
プログライドのヘッド構造にあると言ってよい。
- 肌への追従性が高い
- サスペンションで刃圧が安定
- 少量のジェルでも滑りが良い
- 角度のブレを自然に吸収してくれる
鏡がなくても剃れるくらい扱いやすく、
風呂の外でも安心して使えました。
■ 2. Cica Shaving Gel(メントール)
——水が少なくても、T字を安全に動かせる

今回の仕組みのもう半分を担うアイテムがこれ。
- 粘度が高く、ヒゲが飛散しない
- 少量で顔全体に伸びる
- 皮膜がしっかりしているので刃がスムーズ
- メントールの爽快感が想像以上に気持ちいい
洗面台の蛇口からちょっと水を使う程度で、
問題なく剃れます。
■ 3. ビオレ Bioré Zero フェイスシート
——“洗顔ができない”という最大の問題を解決

正直、これが最も意外なヒットでした。
- ジェルをしっかり拭き取れる
- カミソリの刃も拭ける
- 化粧水入りで保湿もできる
- 香りと清涼感が強くて気持ちいい
- どこでも使える携帯性
風呂の外でT字を使うとき、
最大の課題は「洗えないこと」です。
その問題をこの一枚が完璧に解決してくれました。
■ 4. IKKEI 石鹸ケース
——濡れたT字を“安全にしまえる”小さな便利さ

IKKEIの石鹸ケースは、
今回の構成の中で “T字カミソリの置き場所問題” を解決する役割を担います。
- 濡れたカミソリをそのまま収納できる
- 収納している間に乾く
- 密閉性が高く、カバンや洗面所を汚さない
- 外出先でも安全に持ち歩ける
- とても丈夫で安心感がある
特に驚いたのは、「石鹸が乾く」という点です。
ジップロックのような密閉袋は、濡れたものを入れておくと次に使うまでずっと湿ったままですが、IKKEIの石鹸ケースは違います。防水なのに通気性があるようで、入れっぱなしにしていても、次に使う頃にはちゃんと乾いている。
不思議ですが、これが本当に便利なんです。
ジェルやシートは人によって持ち運び方が変わると思いますが、
カミソリ本体だけは、このケースに入るだけで
どこでも使える道具に変わる。
なお、工夫次第では、
小分けボトルやポケットシートなどと組み合わせて
“ひとつの携帯セット”として発展させることも可能です。
Lサイズなら、ビオレのシートも丸っと入ります。
■ 実際に使ってみた感想:
洗面台なら完璧。ベッド上は“不可能ではないがやる必要はない”。
最初に“極限条件”として試したのは、
- 鏡なし
- 水なし
- ベッドの上
という環境。
結論:
不可能ではない。だが、そこまでする必要はない。
ただ、以下はしっかり確認できました:
- 飛散しない
- 無音
- 肌も荒れない
- 剃り残しも指の感触でほぼ対応できる
けれど実運用として現実的なのは、やはり:
- 洗面台
- トイレ
- パウダールーム
- ホテルの洗面台
- 車内(停車時)
こういう環境でした。
特に、自宅の2Fにある洗面台で
“思い立ったらすぐ剃れる” のは
想像以上のメリットでした。
■ この方法が役立つシーン(まとめ)
- 朝風呂に入れなかった翌朝
- 出勤前に鏡の前でちょっとだけ剃りたい
- 営業前にオフィスのトイレで
- デートの前に身だしなみを整えたい
- 旅行中、風呂のタイミングがズレた日
- ホテルで同室者が寝ているとき
- 飛行機や夜行バスなど、音を出したくない場所
- 昼過ぎに“青ヒゲ”が気になる体質の人
- 車移動中のSA・PA(停車して)
「静かで、深くて、後処理も楽」
というのは、状況によっては大きな価値になります。
■ 結論:
普段のひげ剃りはそのままに、“ひとつ自由が増える”
今回の方法は、
普段のひげ剃り習慣を変えるためのものではありません。
- 電動派の人
- T字派の人
- どちらでもない“なんとなく派”の人
すべての人にとって、
ある特定のシーンだけラクにしてくれる“補助カード” のような存在です。
風呂場だけがT字の居場所ではない。
必要なときに、静かに、どこでも、深く剃れる。
それだけで、ひげ剃りはもう少し自由になる。